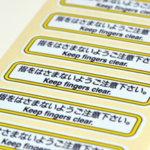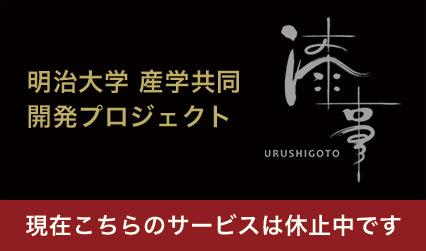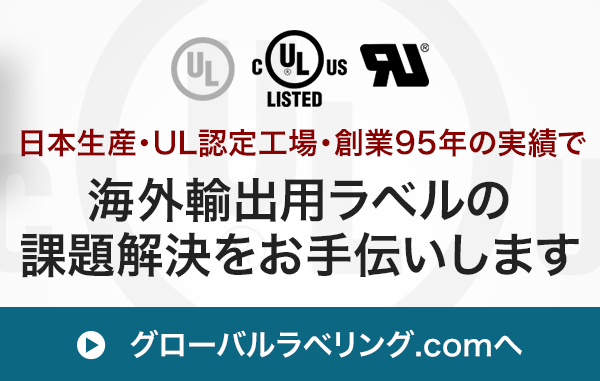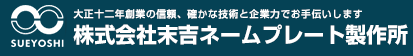測色計について
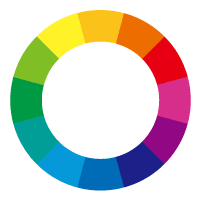
測色計とは、その名前の通り「色」を測定する装置のことです。
抽象的な色を判断する基準は複数ありますが、色の判断基準を数値化し、見る人や場所、条件が変わった場合でも指定通りの正確な色を判断して比較することが可能になります。
印刷を行う上でも色の微妙な差異は製品の仕上がりに響いてくるためとても重要な要素の一つです。
今回は色の判断において有用な測色計についてご説明いたします。
目次
測色計とは
測色計とは、その名前の通り「色」を測定する装置のことです。色を測定する際に、光を当て反射または透過した光の量を捉えて色を定量化する装置です。プラスチック材料や紙、塗料など、様々な物質の色を測定することができます。
色の三属性について
色には様々な名前(呼び方)や表現の仕方があります。色を他者へ説明するとき、「濃い赤」など個人の主観に沿った説明をすることも多いと思います。ただしその場合伝え方があいまいなため、うまく伝わらずお互いの認識に齟齬が起きる可能性もあります。
このようなことがないように、色の三属性として色相・明度・彩度が考案されました。
この属性を用いることで記号や数値で色を表現することができるようになりました。
色の三属性についてご説明します。
色相
「色相」とは、「赤」「青」「黄」などの色みのことを指します。「色あい」とも呼ばれています。
色相とは光による色の変化のことで、その波長の範囲によって無数の色が存在します。
カラーサークルや色相環で表されていることが多いため、目にしたことがある方も多いかと思います。
明度
「明度」とは、色の明るさを表すものです。同じ色相でも、明るさによって見える色には変化があります。一般的に明るい・暗いという表現で使われ、白に近い明るい色を「高明度」、黒に近い暗い色を「低明度」、中間くらいのものを「中明度」と表現します。
彩度
「彩度」とは色の鮮やかさや混じりけのなさのことを表すものです。彩度が低いということは鮮やかでないということになります。彩度が高いことを「高彩度」と呼び、鮮やかで鮮明な色になるのが特徴です。反対に彩度が低いことを「低彩度」と呼び、くすんだような混じりけのある色になっていきます。
上記の三属性を組み合わせることで様々な色を作り出すことができます。
色の正確な判別方法
色は抽象的なため、人の目で見ただけでは正確に判別することは非常に難しいです。そのため判別方法として、「色相」「明度」「彩度」から色を数値化することにより正確に色を判別することができるようになります。屋内では同じ色に見えた場合でも屋外で太陽光にかざしたら違う色だったといった現象があります。色を数値化することによって、そのような微妙な色の違いを判別し、より正確な製品製作につながります。
測色計は微妙な色の違いを判断できる装置
今までご説明した通り、測色計はより正確な色表現をするうえで重要な役割を担う装置です。
ロットごとの色のばらつきが気になる場合や、同じ装置に設置する製品の色味が合わないなどお悩みがございましたら、ぜひお気軽にお問合せください。
また、末吉ネームプレートではシルク印刷、シール印刷、金属銘板など様々な製品を取り扱っております。製品の製作実績をご紹介いたします。
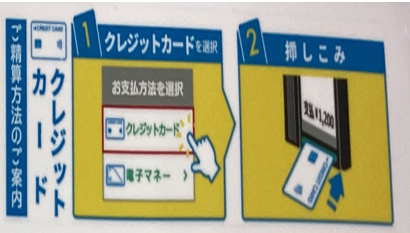
| 製品分類 | ラベル |
|---|---|
| 素材 | JS 1000A |
| 使用環境 | ‐ |
| 仕様・規格 | ‐ |
| 製作方法 | インクジェット |
| 業界 | ‐ |
| サイズ | ‐ |
インクジェット機によって紙材や樹脂材などへのカラフルな印刷を行っています。

| 製品分類 | 説明銘板 |
|---|---|
| 素材 | ステンレス |
| 使用環境 | 屋外 |
| 仕様・規格 | 耐候性 |
| 製作方法 | エッチング |
| 業界 | 交通 |
| サイズ | 120mm×90 |
金属の材料に対して視認性を考慮した黄色の印刷を採用しております。また、屋外で使用されるため、長期間使用し続けられるよう、耐食性に優れたステンレスの材料を使用しております。
末吉ネームプレート製作所では、お客様のご要望・仕様に応じて、高品質な製品をご提供致します。是非一度ご相談下さい。
>>>お問合せはこちら